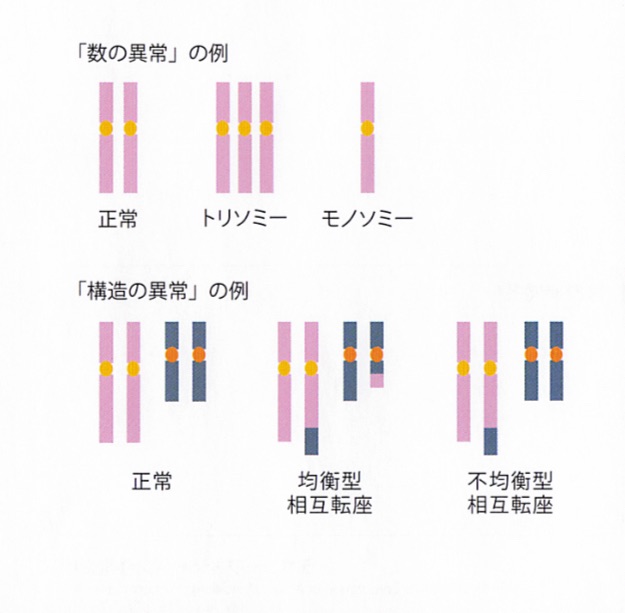こんにちは、副院長の石田です。
母子手帳を使う初めての妊婦健診では診察以外にも様々な検査を行いますが、そのうちの一つが血液型の検査です。若い妊婦さんだとご自身の血液型をそこで初めて知る方も少なくありませんが、占いで使うABOの血液型と違ってRh型の方はなんとなく言葉は知っていても具体的に何なのかはよく分からないことが多いと思います。そこで本日はRhの血液型と妊娠について解説したいと思います。
Rh式の血液型とは?
一般的に血液型といえば占いでもお馴染みのABO式ですが、医学的にはABO式を含めて43種類の血液型分類が確認されています。そのうちの一つがRh式の分類ですが、ABO式がA、B、O、ABの4種類なのに対してRh式では45種類以上の抗原が存在します。その中で普段注目されているのはD型の抗原であり、検査結果の報告用紙に書いてあるRh(+)/(-)というのはRh式血液型の中のD抗原についてあるかないかを示しています。
妊娠とRh血液型について
Rh(-)の方がどのくらいいらっしゃるかについては民族間で割合がだいぶ違っており、日本人では0.5%程度しかいないのに対して欧米の白人だと15%くらいとされています 1)。いずれにしてもRh(+)が多数派ですが、Rh(-)の女性とRh(+)の男性の間に子供ができた場合、(+)の遺伝子の方が強いため赤ちゃんも高確率でRh(+)となります。するとRh(-)の妊婦さんの免疫システムは赤ちゃんのRh(+)の血液を攻撃、破壊してしまうため赤ちゃんの健康に深刻な問題が生じることがあるのです。(逆にRh(+)が(-)を攻撃するということは起こらないのでRh(+)の妊婦さんが知らずにRh(-)の赤ちゃんを妊娠していても問題にはなりません。)
ABO式の血液型が違うのは大丈夫なのか?
ところでRh式よりよっぽど母子の違いが発生するABO式の血液型の違いが問題になりにくいのはなぜでしょうか?それはRh(+)に対する抗体がIgGという小さいサイズのもので胎盤を通過してしまうのに対してABO式の違いで発生する抗体はIgMという胎盤を通過できない大きなサイズの抗体であるため赤ちゃんに影響を及ぼしにくいという特徴があるからです。
まとめ
本日は意外と知らない血液型のお話でした。妊婦健診の検査結果にサラッと書いてあるあのマークにはそんな背景があったんですね。Rh(-)の女性が妊娠した場合には赤ちゃんのリスクを軽減するために必要な処置を行いますが、それに関しては回を改めて解説いたします。いずれにしても該当する女性は主治医とよく話し合って慎重に妊娠を進めていきましょう。
1) Arch Dis Fetal Neonatal Ed. 2011 Mar;96(2):F84-5