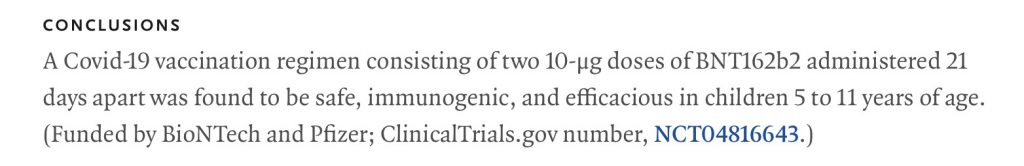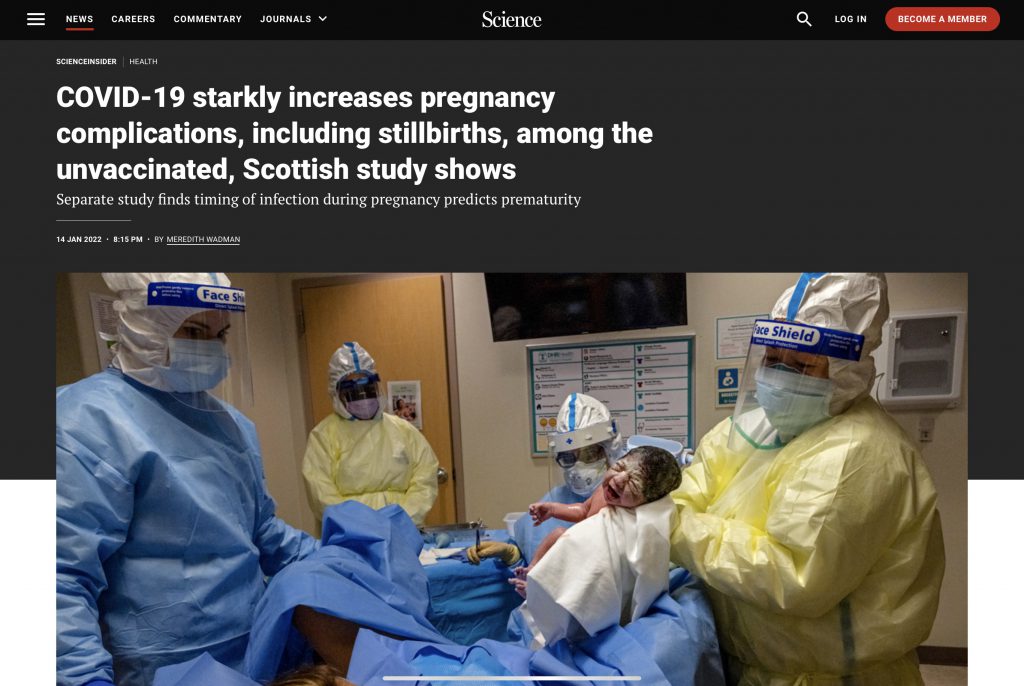こんにちは、副院長の石田です。
なんか最近また新型コロナウイルス感染症の患者さんが少し増えてきているのかなという雰囲気がありますが、皆さんは元気にお過ごしでしょうか?2020年から社会全体がパンデミックにより振り回されてきたこともあり、もう名前も聞きたくないという方も多いかもしれませんが、最近の学会誌でこれまでの妊婦さんとコロナの状況についてデータをまとめた論文が出ていたので内容を簡単にご紹介してみようと思います 1)。
妊婦におけるCOVID-19の発生状況
実は国内の妊婦さんにおけるCOVID-19の罹患数についての統計は報告されていません。「あんなに毎日書類書いてどこかに送ってたのに…。」とか思うんですが、全期間を通したレジストリ登録妊婦の重症度別割合を解析すると軽症(咳のみ)が85%、中等症I(呼吸困難あり)が8.2%、中等症II(酸素投与)が6.2%、重症(人工呼吸器やECMOを使用)が0.65%ということでした。ただ、中等症II+重症の割合はデルタ株(第5波)で20%だったものの、オミクロン株(第6波)以降では1%未満と急激に低下したそうです。
妊婦のCOVID-19 重症化リスク
上記の通り、第6波以降で感染した方は明らかに重症度が低いです。ワクチンに関しては接種歴不明を除いて解析すると、中等症II・重症は1回以上接種者で0.39%に対して非接種者10%と有意に差があったようです。そのほか、重症化リスクとしては妊娠前半(21週未満でリスクが6.5倍)、体格(BMI≧30でリスクが2.8倍)、年齢(31歳以上で2.8倍)、妊娠前からの基礎疾患の有無(基礎疾患有りで2.5倍)などが挙げられたそうです。一方で妊娠に伴う産科合併症(妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群、切迫流早産など)に関してはCOVID-19の重症化とは関係なさそうということでした。
まとめ
本日は今さらだけど妊娠とコロナについての振り返りをご紹介してみました。どれも皆さんの肌感覚に概ね合うデータなんじゃないかなと思いますがいかがだったでしょうか?コロナだけでなくインフルエンザやマイコプラズマ、最近ではりんご病など様々な感染症が流行っていますが、妊婦さん本人はもちろんご家族も含めて十分注意しながら快適なマタニティライフをお過ごしください。
参考文献
1) Masashi D. Acta Obst Gynaec JPN 2024;76(12):1711-1716.