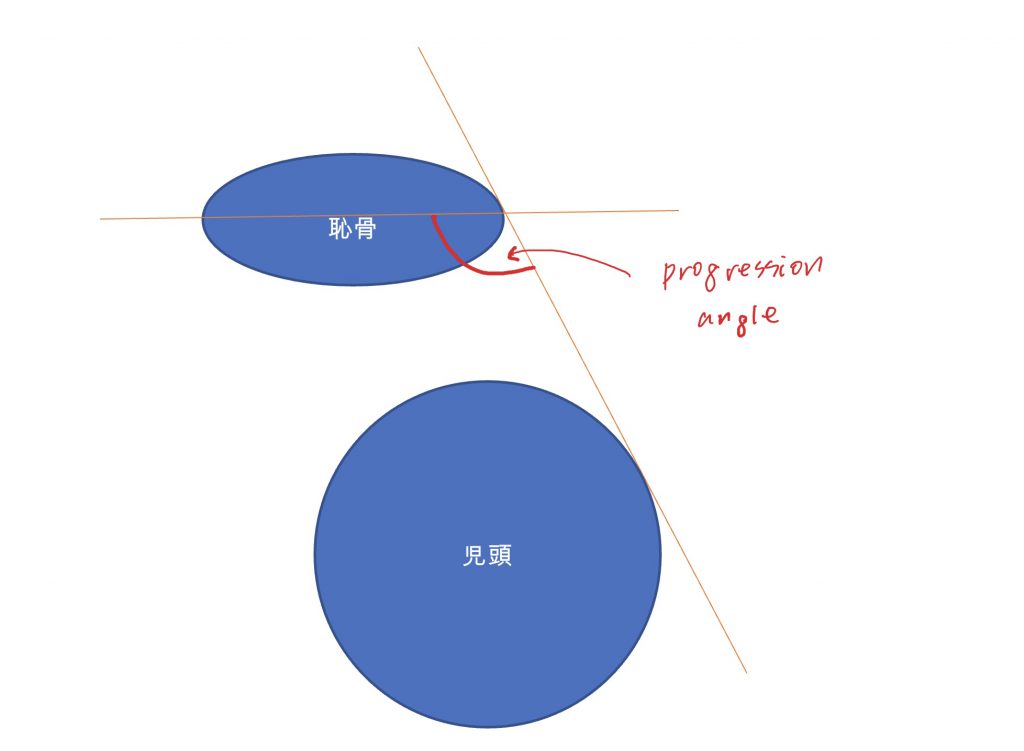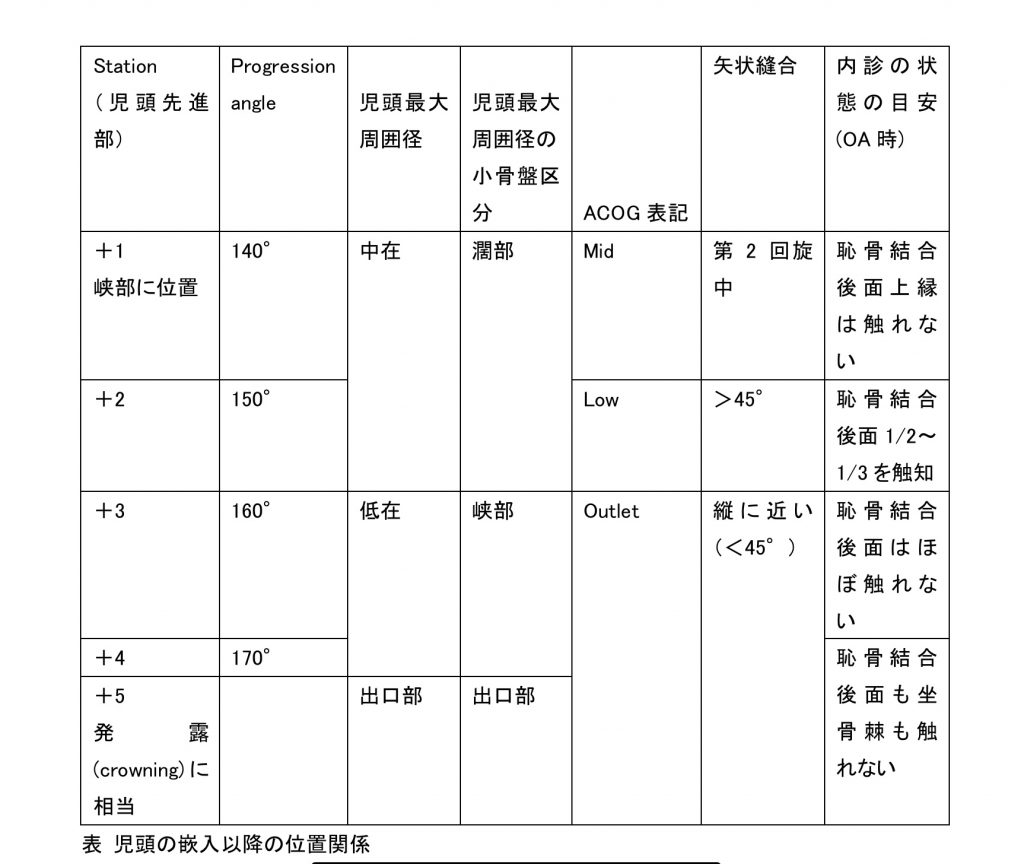こんにちは、副院長の石田です。
当院では入院中の患者さんをメインにアロマテラピーを提供しています。お産中から産後にかけて専門のセラピストが医療者と協力しながらケアにあたらせていただいていますが、そもそもアロマとお産にどういう関係があるのでしょうか?というわけで本日はこのことについて少し解説させていただきます。
アロマセラピーとは
日本アロマ環境協会のウェブサイトによると、「アロマテラピーは植物から抽出した香り成分である精油(エッセンシャルオイル)を使って、美と健康に役立てていく自然療法」とあります 1)。“アロママッサージ“と聞くとエキゾチックな香りのするオイルを使用したタイマッサージを連想する人も多いかもしれませんが、グイグイ体のツボを押すようなマッサージではなく、むしろそれぞれのオイルが持つ香りの力を使って中枢神経を刺激したり、オイルが皮膚を通して作用することにより心身を整えていくのがアロマテラピーということです。
アロマセラピーとお産
陣痛という強い痛みの中でアロマの香りなんか楽しめるのだろうかと心配になる方もいらっしゃると思いますが、実はアロマオイルを使用することにより陣痛が緩和できるというデータがあります 2)3)4)5)。陣痛に対する恐怖感や緊張感が強いと交感神経がその分強く刺激され、それによって分泌されるアドレナリンやノルアドレナリンなどのストレスホルモンが陣痛を増強すると言われていますが、アロマオイルの香りとセラピストによるケアにより妊婦さんがリラックスすることで陣痛緩和効果が得られると考えられているわけです。陣痛でパニックになると呼吸法などの指導が入らなくなってしまう方もいらっしゃいますが、アロマオイルであれば嗅覚を通じて確実に届きますし、肌に合わないなど局所の問題が無ければ副作用も無く安全に使用できるのも利点ですね。
お産後のアロマも大切
お産は心身ともに大きく消耗するイベントですが、そこから一息つく間も無くすぐに育児を始めなければなりません。そのため入院中を含めていかにお母さんの心と体を回復させるかが課題となりますが、その場面でもアロマの有効性が示唆されています。具体的にはアロマテラピーを行うことでお母さんのストレスや鬱っぽさが改善したり、睡眠の質が高まったりするそうです 6)7)。そのため当院では分娩後の患者さんに対してもアロマテラピーやシッツバス、病室でのディフューザーによるアロマサービスなどを行っています。
まとめ
実際の臨床経験ではやはり緊張が強い妊婦さんのお産は痛みが強かったり進みにくかったりする印象があるため、我々医療者は妊婦健診を通じて信頼関係を築く、両親学級で出産の流れをイメージしやすくする、陣痛中のケアを行う、(今はコロナのせいで難しいけど)立ち会い分娩を奨励するなど様々な手段を使って妊婦さんをリラックスさせようと努力しています。上でお示ししたデータは必ずしもエビデンスレベルが高いものではありませんが、その一方で「アロマに助けられた」と言ってくださる患者さんも多く、嗅覚や触覚からの効果を期待できるアロマテラピーはお母さんと赤ちゃんを守るのにとても有効な手段であると確信しています。当院では国内外の資格を有するセラピストが医療スタッフとの連携のもと、皆さん一人ひとりの症状や好みに合わせて適切なアロマオイルをご提案しながらただのオイルマッサージとは違う本質的なケアを提供しています。ご興味のある方は是非当院のウェブサイトもご覧ください。
1) 日本アロマ環境協会:https://www.aromakankyo.or.jp/basics/introduction/
2) Tabatabaeichehr M, et al. Ethiop J Health Sci. 2020;30(3):449-458
3) Rajavadi Tanvisut, et al. Arch Gynecol Obstet. 2018 May;297(5):1145-1150
4) Masoumeh Namazi, et al. Iran J Pharm Res. 2014;13(3):1011-1018
5) Masoumeh Namazi, et al. Iran Red Crescent Med J. 2014 June;16(6):e18371
6) Kianpour M, et al. Iran J Nurs Midwifery Res. 2016 Mar-Apr;21(2): 197-201
7) Mahnaz Keshavarz Afshar, et al. Iran Red Crescent Med J. 2015 Apr;17(4):e25880