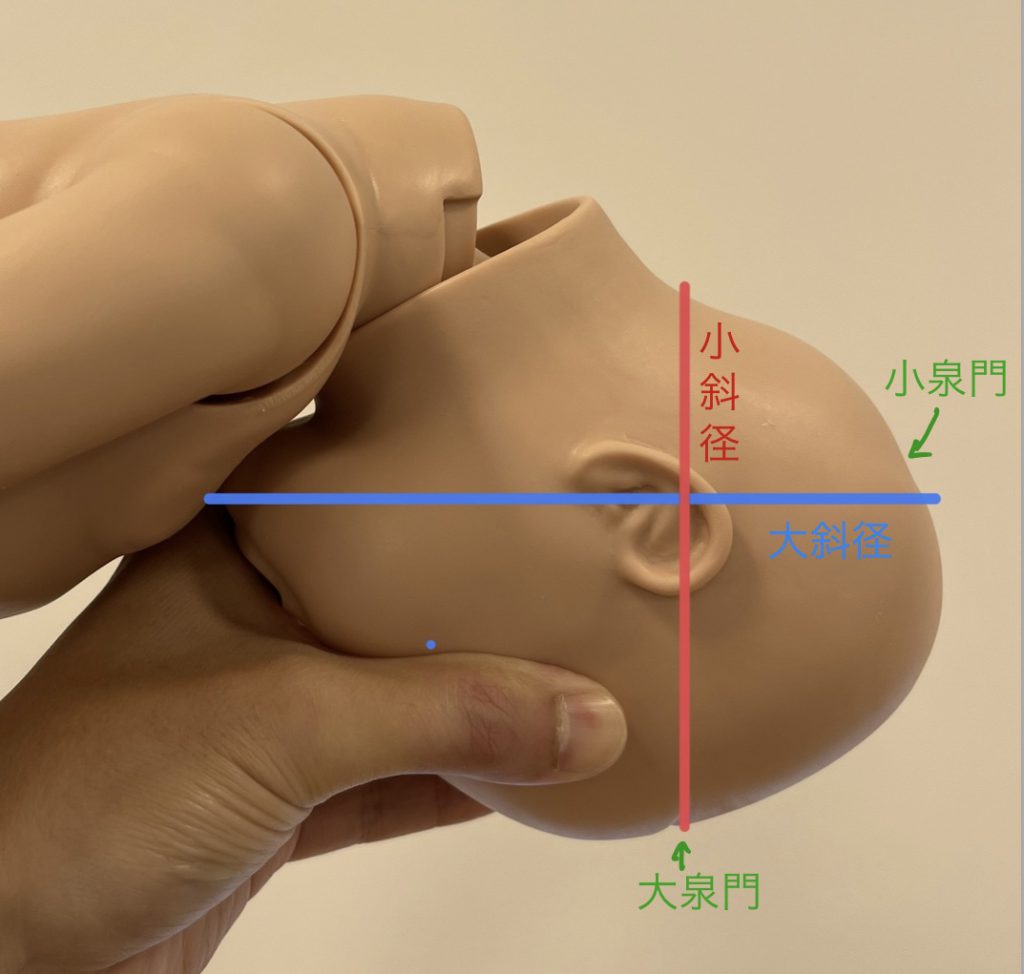新型コロナウイルス感染症治療薬として、経口抗ウイルス薬のモルヌピラビル(ラゲブリオ®︎)の一般流通(*)が開始されました。
(*卸販売業者を通じて医療機関および薬局に納入が開始され、
通常どおり医師が処方箋を発行し、お薬を出す、ということです1)。)
モルヌピラビルの薬効動態
モルヌピラビルはRNA合成酵素阻害薬です。新型コロナウイルスにおけるRNAポリメラーゼに作用し、ウイルスRNAの配列に変異を導入し、ウイルスの増殖を阻害します。
発症後、なるべく早いうちに服用することが推奨されています。
モルヌピラビルの処方を適さない方
動物実験で胎児毒性が報告されており、妊娠中は禁忌(使用できない)となります。
ということは、妊娠中は新型コロナウイルス感染症の重症化リスクを下げるためにはワクチン接種が手立てとなります。
なお現時点では18歳以上の方が処方を考慮する対象となります。
一般流通品となり、何が変わるのか
経口抗ウイルス薬としてのアクセスが容易になれば、たとえ妊婦さんがモルヌピラビルを使用できなくても家族が新型コロナウイルスにかかった場合、早めの内服でウイルスの拡散を低くすることが可能と考えます。
文責 院長
引用文献
1) 新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬(飲み薬)について. 神奈川県HP