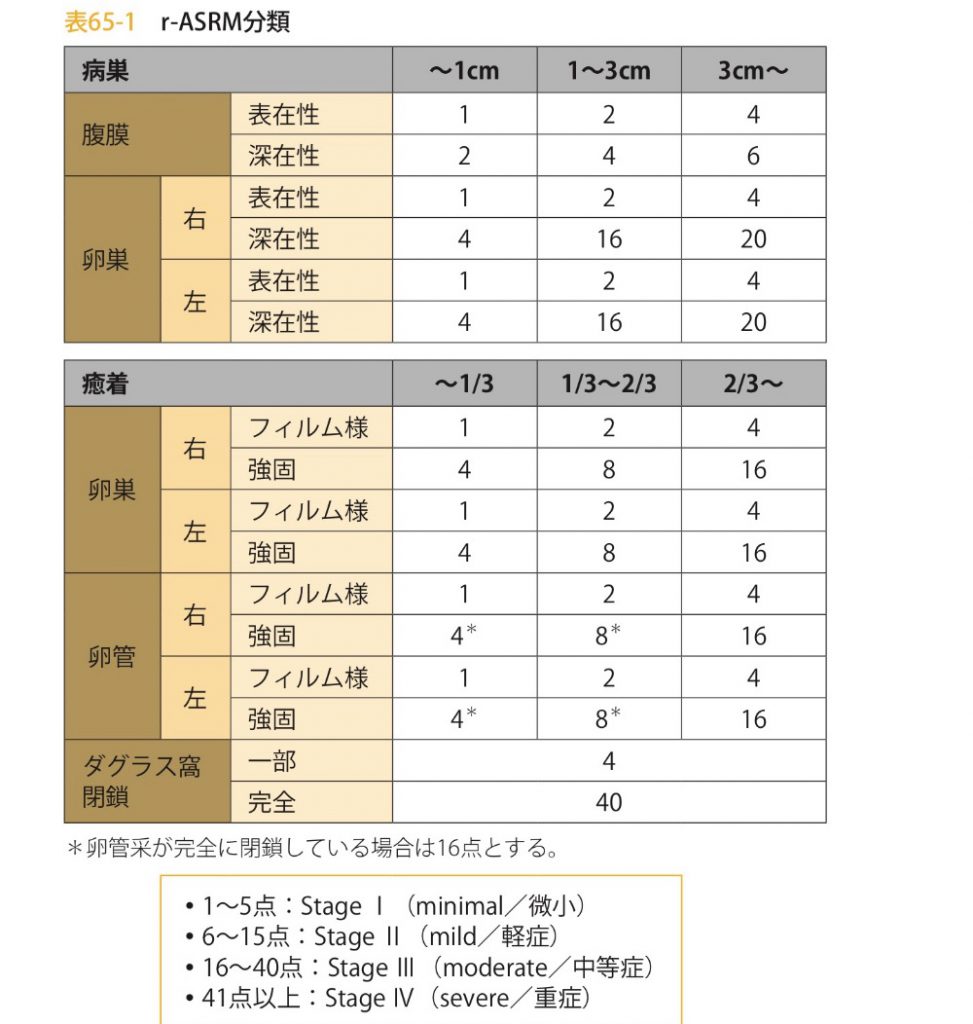こんにちは、副院長の石田です。
当院が担当させていただいている埼玉県富士見市、ふじみ野市、三芳町では毎年6〜11月に、生まれ月で振り分けた20歳以上の女性を対象に2年に一度子宮頸がん検診を行なっています。(今年の対象は奇数月生まれの人です。)今年もたくさんの方に検診で来ていただいていますが、その際によく聞かれるのが「今生理中なんですけど検査できますか?」という質問です。そこで本日は生理中の子宮頸がん検診についてお話ししたいと思います。
生理中の子宮頸がん検診の問題点
子宮頸がん検診は腟内に出ている子宮の出口の部分をブラシや綿棒で擦って細胞を採取する検査です。その細胞を顕微鏡で見て悪い特徴が無いかを確認するのですが、生理などで赤血球が多量に混ざるとそれが邪魔をして子宮由来の細胞がよく見えなくなってしまうんですね。そのため患者さんが当日生理になってしまっている場合は検査を断るという病院や自治体も多くあります。
生理中は本当に検査ができないのか
実は生理中でも絶対検査ができないというわけではありません。厳密に言うとそれぞれの施設で行なっている検体採取の方法によって変わるのですが、生理による検査結果への影響は見られなかったという臨床研究があるほか、アメリカの政府系保健組織であるCDCのウェブサイトでも「生理中でも検査は受けられるので心配しないでね!」と記載されているんですね 1)2)。これらを踏まえて私は、患者さんの子宮頸がん検診の日が生理と重なってしまった場合はブラシで擦る前に子宮口を丁寧に拭ってから検査するようにしています。実際それで判定不能として結果が返されたことはありません。
まとめ
本日は生理中の子宮頸がん検診についてお話ししました。確かに生理ではない日に検査できるのがベストですが、忙しい中でそこまで考えるとなるとスケジュール調整が難しいという方も多いと思います。そのため私はよほどの状況でなければ検査をして帰っていただくようにしていますが、一方で施設によっては上記のように再予約をお願いされることも少なくありません。実際、米国産科婦人科学会や日本医師会などのウェブサイトでも「検査は受けられるけど、できれば生理中の検査は避けてね」とされていますので、皆さんにおかれましては可能な範囲で出血の無さそうな時期を狙って予約されることをお勧めいたします 3)4)。
参考文献
1) M E Sherman, et al. Br J Cancer. 2006 MAy 2;92(11):1690-1696
2) CDC. Screening for Cervical Cancer.
3) ACOG. Cervical cancer screening.
4) 日本医師会. 子宮頸がん検診Q&A