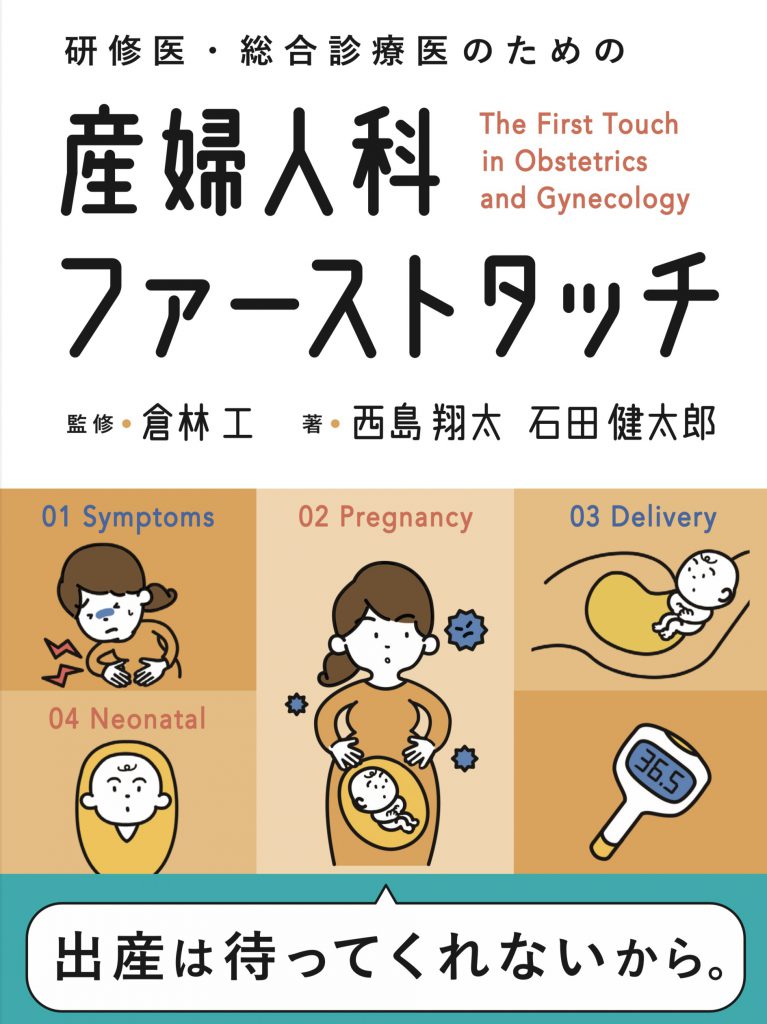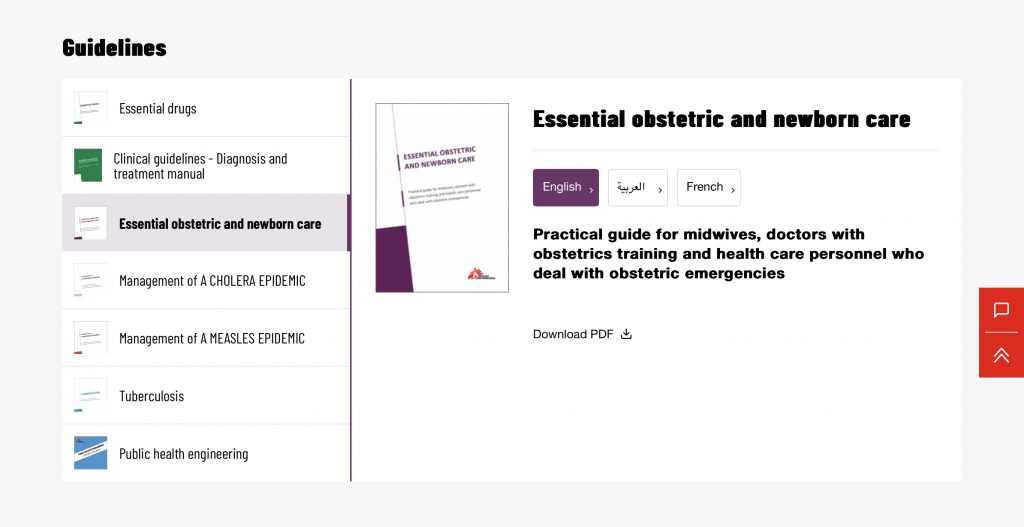こんにちは、副院長の石田です。
予定日超過などの何らかの医学的な理由や無痛分娩を含む社会的な理由で分娩誘発を行う妊婦さんは少なくありません。そんな時に使用するのが子宮収縮薬と言われるお薬です。このお薬にはいくつか種類があって、医師は病歴や診察所見をもとにその患者さんに最も望ましいと思われるものを選択して使用します。医師によって選び方に個性がありますが、大雑把な使い方は共通しているため我々からすると個々の患者さんの使用薬剤を見るだけで現在の状況がざっくりと把握できます。しかし患者さんからするとどんな理由で昨日と今日の子宮収縮薬が違うのかが分かりにくくて不安になるかもしれないので、本日はこれについて少し解説したいと思います。
プロスタグランジンとオキシトシン
子宮収縮薬にはおおまかにプロスタグランジンとオキシトシンという2種類の薬剤があります。いずれも分娩の進行に重要な役割を担うホルモンで、本来は体内で自然に分泌されて陣痛発来に寄与しますが、人工的に陣痛を起こしたい場合にはお薬として妊婦さんに投与します。細かい使い分けは長くなるので割愛しますが、プロスタグランジンは現在点滴で使用する注射薬、口から飲む経口薬、腟の中に入れて使用する坐薬の3種類が日本で使用できます。
ところで、分娩の三要素という言葉をご存知でしょうか?娩出力(陣痛の強さ)、産道(赤ちゃんの通り道)、娩出物(赤ちゃん)という3つの要素が噛み合って初めて分娩は成功するということで、要は陣痛が弱い、産道が通りにくい、赤ちゃんの大きさや向きが良くないなどどれか一つでも状況が許さないと赤ちゃんは生まれてきてくれないわけですが、プロスタグランジンはこの中で産道の状態を改善する力が大きいとされています。そのため「子宮の出口が固く閉じてて陣痛を起こしても出てこられなさそう」という患者さんにまず使うことが多いです。この製剤は永らく点滴薬と経口薬のみでしたが、最近になって世界に遅れて日本でも経腟坐薬が発売され使われ始めました。坐薬に関しては国内では新しい薬なのでなかなか使い方に迷う施設が多いと聞く一方で、院長と私はそれぞれ海外で似たような薬を使い慣れていたためか、気がつけば意図せず当院が県内で最も使用実績のある施設となっているようです。
オキシトシンは点滴薬で、陣痛(娩出力)を強くする効果がとにかく強いです。また、プロスタグランジンよりも使用に関しての制限が少なく使いやすいのも特徴です。その一方で子宮の出口を開きやすくする効果はあまり期待できないため、「既にある程度出口が開いていて、あとは赤ちゃんを押し出してあげるだけ」という状況で使うことが多いです。
まとめ
というわけで本日は分娩誘発に用いられる薬剤について解説しました。まとめると、分娩誘発の基本戦略は様々な方法で産道を通りやすくしてから最後にオキシトシンで陣痛を誘発してお産にするというのが一般的です。子宮の出口である頸管はBishop scoreという国際的に用いられる指標で6点以上なら熟化しているとみなされますが、薬剤の種類や剤型の選択は子宮頸管の状態だけでなく妊婦さんの年齢、週数、経産数、体型、基礎疾患の有無、そして赤ちゃんのサイズ等様々な要因を考慮した上で医師の経験や好みも織り交ぜて決定されます。子宮収縮薬に関しては各種メディアで定期的に危険性が訴えられることで何か悪役のような扱いを受けることがありますが、使用基準や方法は膨大に積み上がったエビデンスに裏打ちされたガイドラインで厳格に定められており、適切に使用される分には極めて安全な薬剤です。それどころかこれらの薬がなければ多くの母子の命が失われていたことに疑いの余地はありません。分娩誘発と言われるとなんだか怖くなってしまう人もいるかもしれませんが、主治医によく話を聞いた上で安心して臨んでいただければと思います。