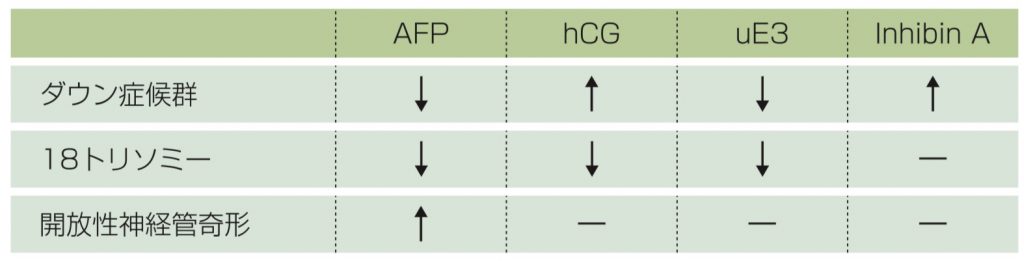こんにちは、副院長の石田です。
今年は元旦から能登半島で大地震がありましたが、8月8日にも宮崎県沖で地震が発生し、かねてより来るぞ来るぞと囁かれてきた南海トラフを震源とする大震災との関連が危惧されています。そうでなくとも日本は自然災害の多い国ですが、当院では以前よりそれらに対してできる範囲での備えを行ってきました。そこで本日は皆さんににしじまクリニックの災害対策について少し紹介してみたいと思います。
自然災害により想定される被害
当院は富士見市勝瀬にありますが、富士見市が発行するハザードマップによるとこの地域は地震、水害、土砂災害のいずれにおいても最も想定被害が軽いレベルに分類されており、比較的安全な施設であると言えます 1)。建物自体も2005年にコンクリート製で建てられているため、地震による倒壊の危険性も極めて低いと考えられます。
災害への備え
そうは言っても何があるか分からないのが自然災害です。私は2011年の東日本大震災の際に現地でボランティア活動を行いましたが、そこで目にした自然の猛威による痕跡は想像を絶するものでした。そのため当院でも万が一に備えて食料や医療備品の在庫を多めに確保することでいざという時の備蓄としたり、発電・送電インフラが破壊された時に手術室や新生児室など重要度の高いところへの電気供給ができるよう自家発電設備を導入しています 2)。地震で直接の被害がなくても火災などが二次的に起こる可能性は否定できないため院内で年2回の避難訓練も実施し、その都度課題を洗い出しては避難マニュアルをアップデートし続けています。
まとめ
今回は当院における災害対策についてお話ししました。クリニックレベルでの備えはもちろん大切ですが、自然災害では広範囲に被害が出るため地域での協力も欠かせません。そのため埼玉南西部医療圏に位置する産科医療機関間でも定期的に合同会議を行い、災害時に地域の妊産婦さんをいかに守っていくかについて話し合っています。ただ、その一方で災害時には自分の安全は自分で守る必要があるのも事実です。妊婦さんや小さな赤ちゃんがいるご家庭は通常の備えに加えて特別な準備が要りますので、皆さんもこの機会に是非ご自宅の備えやいざという時の動線を確認してみてください。