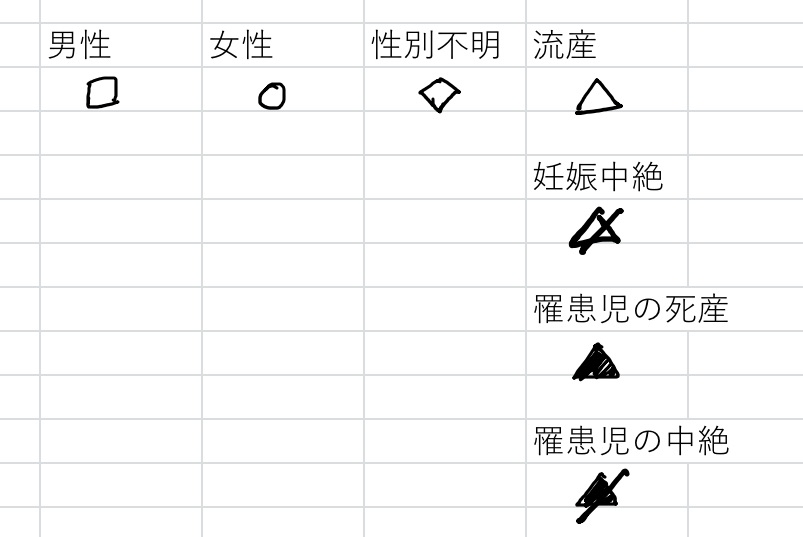こんにちは、副院長の石田です。
最近「卵子凍結」という言葉がちらほら見られるようになりました。結構前から子供を含めたがん患者に対する医療としての卵子凍結は一般的に行われていましたが、最近は病気でない女性の卵子凍結が注目されているように思います。実際、私も知人から「卵子凍結に興味があるんだけど」と相談されることが何回かありました。そこで本日は卵子凍結についてお話ししてみようと思います。
卵子凍結とは
排卵誘発などを行い採取した卵子を未来の妊娠のために凍結保存する医療技術です。リアルタイムで新しく作り続けられる精子と違い、卵子は女性が生まれつき卵巣内に持っている分が全てで新たに作られることはありません。そのため卵子は持ち主の女性と一緒に加齢していきます。また、胎児期の卵巣内に約500万個ある卵子は、生まれた時には約100万個にまで減少しています。そして思春期には10万個程度まで減っており、1000個程度になると閉経すると考えられています。つまり卵子は時間経過とともに質と量の低下を受けるため、女性は歳をとるほど妊娠しにくくなったり、子供の染色体異常が発生しやすくなったりするのです。しかし卵子凍結は採卵時点での卵子の状態を維持できるため、質の低下を止められるわけです。そのため「今は予定が無いけど、将来の妊娠のためにより状態の良い卵子を残しておきたい」と考える女性にとって選択肢の一つとなっているのです。
卵子凍結の注意点
晩婚・晩産化が進む日本社会において、卵子凍結はより良いライフプランニングのための有力な選択肢に思えるかもしれませんが、実際には注意が必要です。まず、卵子凍結は必ずしも未来の妊娠を約束してくれるわけではありません。凍結した卵子を使用する際は解凍した上で体外受精を行い、一定程度細胞分裂させた“胚“を子宮内に移植する必要があります。これらの過程を経て最終的に出産まで辿り着くのは凍結卵子1個あたり10%前後というデータがあり、希望すればすぐに妊娠できるわけではないことが分かります 1)。また、卵子凍結で止められるのは「卵子の時計」だけで、女性の身体そのものの時間は止まりません。そのため母体年齢が高くなるほど医療技術を用いても妊娠が成立する可能性が低下します 2)3)。さらには加齢に伴い妊娠前から何かしらの病気を持っている可能性が高まったり、妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群、早産、産後の大出血など妊娠・出産に伴う健康リスクも増加します。卵子凍結を検討している女性は、あらかじめこれらを十分に理解することが大切です。
まとめ
卵子凍結は様々な社会課題を内包しつつも、治療によって卵巣機能を失う可能性があるがんなどの病気を抱えた女性、性的マイノリティーの方、妊娠を希望しているがまだ良い出会いが無い女性などに、血の繋がった子供を持つチャンスがより多くもたらされるという点で良い医療技術です 4)。事実、ある調査によると卵子凍結を実施したうちの89%の女性が凍結した卵子を使用する・しないに関わらず、より多彩な選択肢を持てたことに満足しているという結果が示されました 5)。その一方でしばしば気になるのが、「卵子凍結をすればいつでも凍結時のコンディションで安全に妊娠できる」という楽観的な誤解を持つ方や、採卵から妊娠・出産に至るまでのリスクに対する理解が足りていないと感じる方が少なくないことです。また、卵子凍結をお考えであっても、状況によってはそもそも自然妊娠や従来の不妊治療で進めるべきと思われる方もいらっしゃいます。選択肢の多い時代だからこそ、皆さんのライフプランにどれが最適な方法かを最寄りの専門施設で相談してみると良いかもしれませんね。
こちらは日本産科婦人科学会による卵子凍結についての解説動画です。非常に分かりやすいと思いますので是非ご覧ください。
→https://www.jsog.or.jp/medical/865/
参考文献
1) Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for Assisted Reproductive Technology. Fertile Steril. 2013 Jan;99(1):37-43.
2) Sarah Druckenmiller Cascante, et al. J Assist Reprod Genet. 2024 Nov;41(11):2979-2985.
3) Angela Q Leung, et al. Reprod Biomed Online. 2021 Oct;43(4):671-679.
4) Sarah Druckenmiller Cascante. Reprod Biomed Online. 2023 Dec;47(6):103367.
5) Eleni A Greenwood, et al. Fertil Steril. 2018 Jun;109(6):1097-1104.e1.