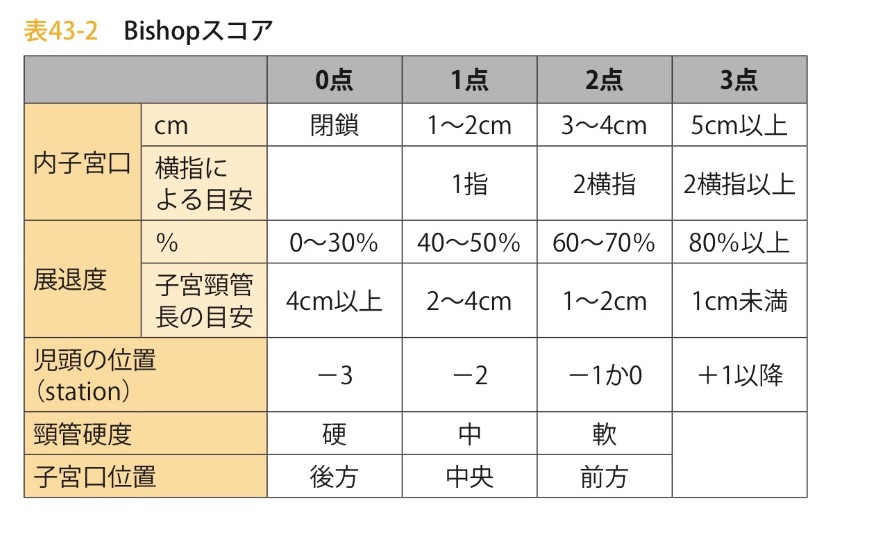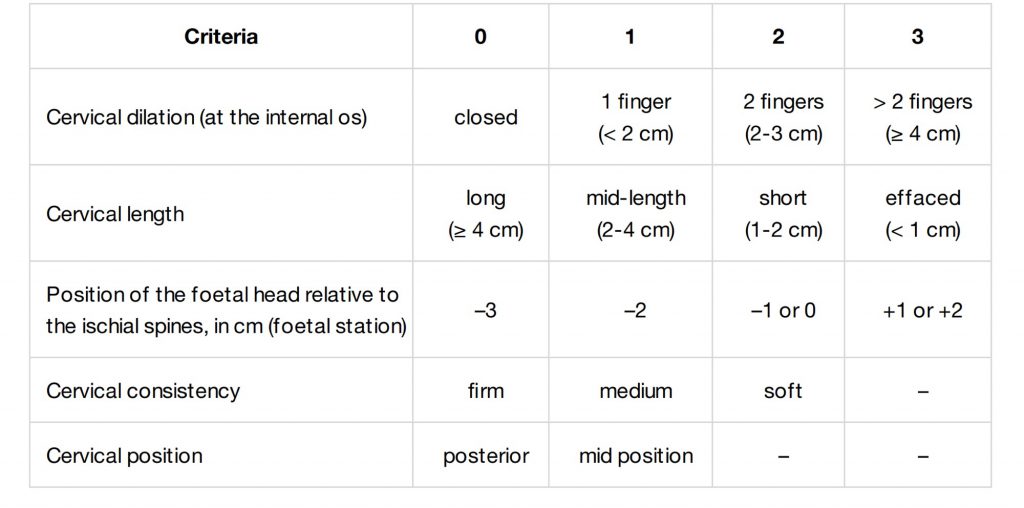こんにちは、副院長の石田です。
お産が近づいてくると気になることの一つに会陰切開があります。会陰切開が分娩時に行われることがある、ということ自体は初産婦の方でも多くが知っているものの、実際に「切る」と想像すると不安や恐怖を感じてしまう人もいるでしょう。そこで本日は、会陰切開をどう考え、どのように向き合っていけばよいのかについて一緒に考えていきたいと思います。
会陰切開とはなんなのか
会陰切開とは、赤ちゃんが産道を通りやすくするために会陰部(腟と肛門の間)をハサミで切開する医療手技のことを指します。経腟分娩を経験する女性のうち、会陰切開の有無にかかわらず実際にはおよそ90%前後の方に何らかの会陰裂傷が生じるといわれていますが、切れ方によっては複雑に広がり治りにくくなるケースもあるため、自然に裂けてしまうよりも重症化しにくい方向へ誘導したり、後で縫合しやすいきれいな傷を作る目的であらかじめ会陰切開を行うことがあります 1)。また、母体や赤ちゃんの状態が悪化し分娩を急ぐ必要がある場合、あるいは吸引分娩・鉗子分娩など補助的な器具を使用する場面でも、安全性を高めるために会陰切開が必要となることがあります。切開を入れるタイミングは、赤ちゃんの頭が降りてきて出そうになる直前で行われるのが一般的です。
会陰切開の実際
いや、会陰切開が医療的に大切な処置なのは知っているんだと。それは分かるんだけどハサミでお股を切るなんて想像するだけで怖いから、できればそんなことしないで欲しいんだよってみなさん思っていることでしょう。そんなお母さんたちにここからは私の超主観的なアンサーになるんですけど、自分はお産前から会陰切開のことなんてあまり気にしなくてよいと考えています。というのも、前提として赤ちゃんが生まれる直前は陣痛もさることながら、腟と会陰も赤ちゃんの頭にゴリゴリ押し広げられてとても痛いんですよ。そんな中で「会陰切開すれば赤ちゃんがすぐ出てくる」「これでお産にしましょう」って伝えて「やらないで!」って断られたことは1回も無いです。というか、なんなら喰い気味に「いいから早く切って!!」って怒られたことは数えきれないほどあります。そのぐらいお産の瞬間って大変なんですよね。もちろん無痛分娩なら切開やその後の縫合も痛くないので気にする必要はないでしょう。会陰切開のリアルな現場はそんな感じなので、お産前からそれを気にし過ぎるよりはもっと分娩中の過ごし方とか楽しいことを考えた方が建設的なのかなというのが私の意見でした。
まとめ
ということで本日は会陰切開について少しお話ししました。たまに会陰切開を入れなければ縫わなくて済むと誤解されている妊婦さんもいらっしゃるのですが、お股を3kg近い赤ちゃんが通過するわけですから、上記の通り会陰切開の有無に関わらずほとんどのお産で大なり小なり切れます。そしてそもそも我々産婦人科医としても、切らなくて済むなら切りたくないんですよ。切らずに裂傷なしでお産になればそれで仕事が終わる上に、患者さんからは(何もやってないのに)名医的な雰囲気ですごく感謝されることが多いからです。それでも時にはお母さんの会陰を深刻なダメージから、そして赤ちゃんの健康を重大なリスクから守るためには躊躇なく行わなければなりません。もちろんその時の声掛けなどを打ち合わせるために当院のバースプランにも会陰切開の項目がありますが、とは言え妊婦さんたちはあまりそこに固執することなく、楽しく分娩に臨んでいただければと思います。
参考文献
1) Nicola Adanna Okeahialam, et al. Am J Obstet Gynecol. 2024 Mar;230(3S):S991-S1004.