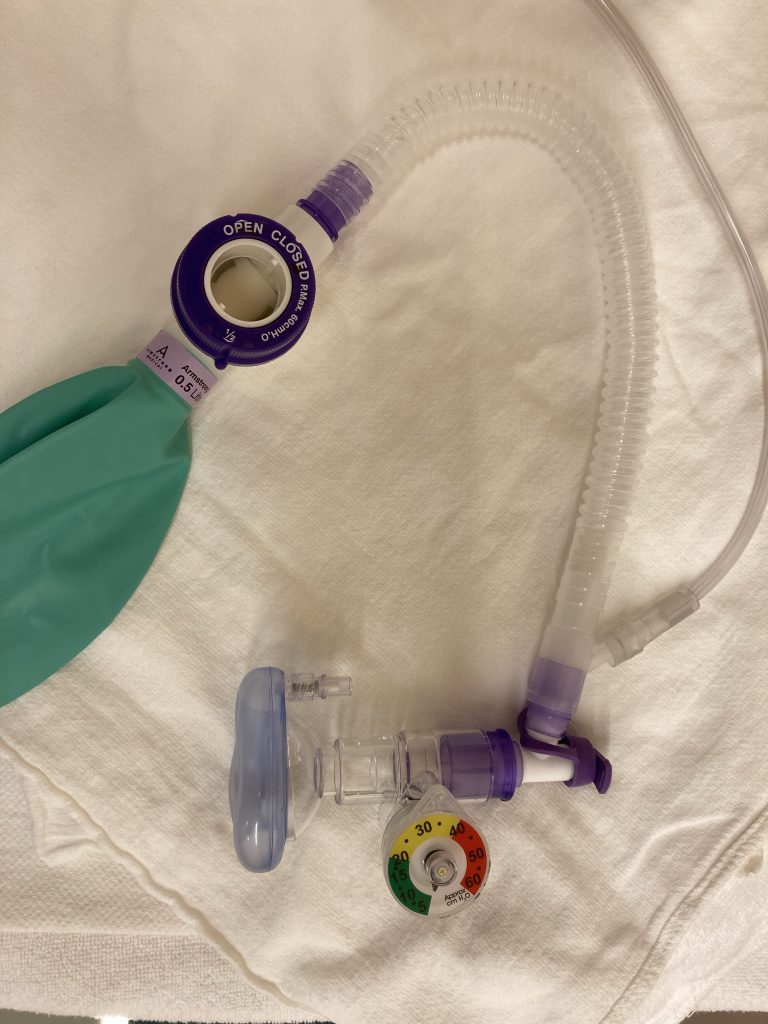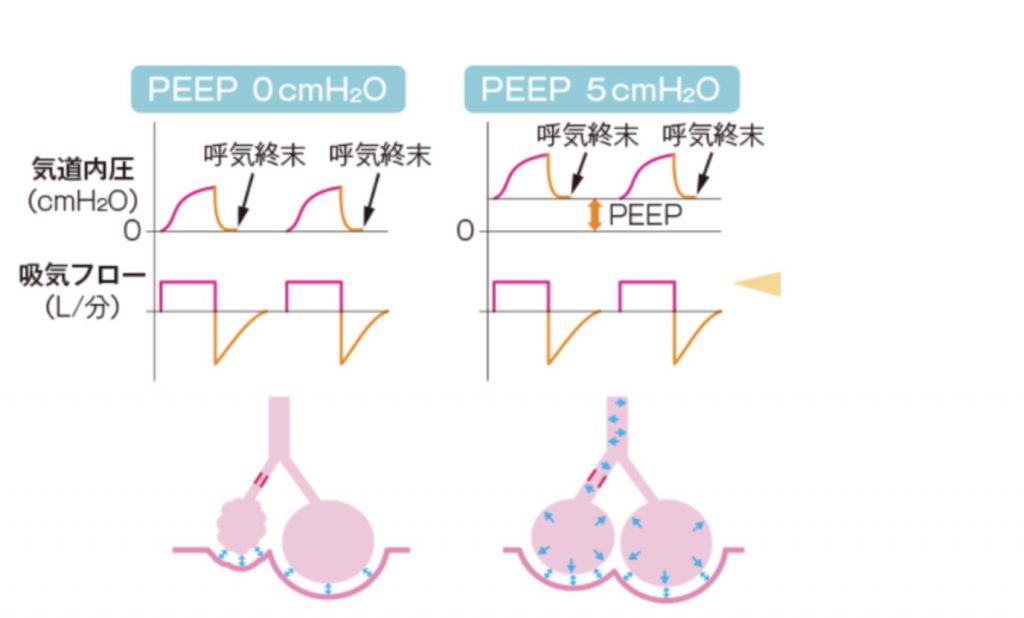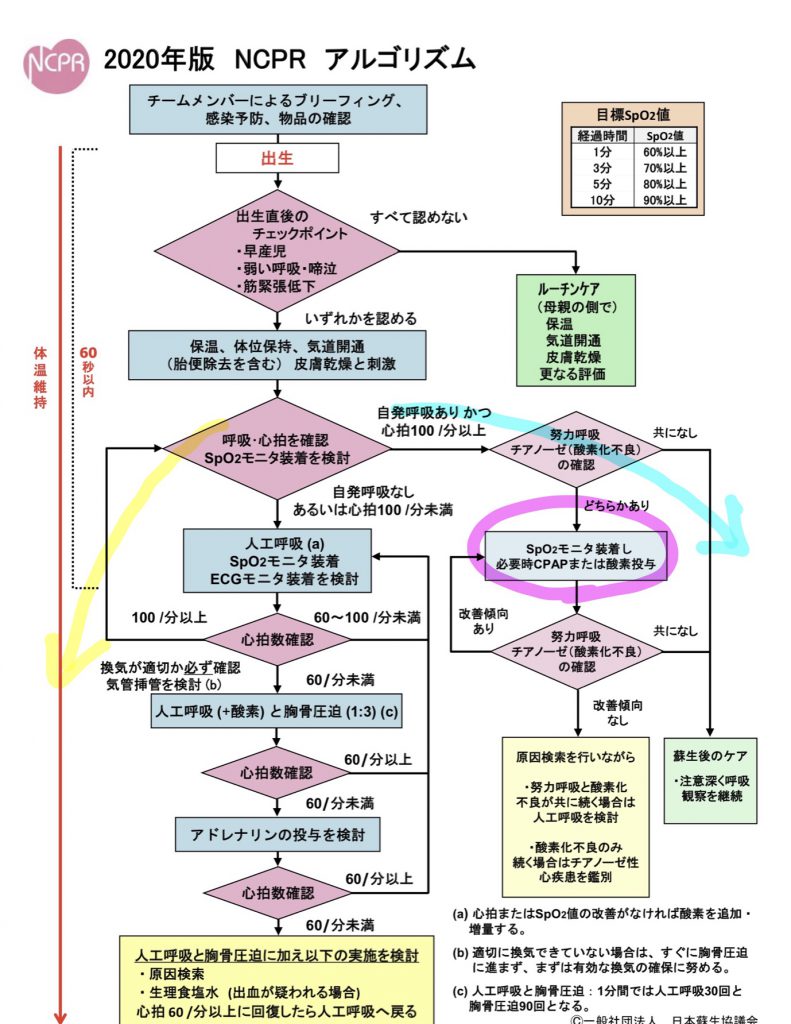こんにちは、副院長の石田です。
当院は最近10代の女性患者さんが増えてきています。婦人科受診が初めてで色々不安という方も多いですが、彼女たちの訴えで最も多いのが生理痛です。そこで本日は思春期の生理痛について少しお話しします。
思春期の生理痛の原因
子宮筋腫や子宮内膜症などが原因で生理が重くなるのを「器質性月経困難症」と言いますが、これらは20代以降によく見られる一方で10代の女性では特に原因疾患が指摘できない「機能性月経困難症」がほとんどです。これは生理中に子宮の筋肉を収縮させるプロスタグランジンというホルモンが体質的に出過ぎる結果、子宮の血流が悪くなることで痛みが強く出ると考えられています。どこまでが普通でどこからが病気という明確な線引きは無く、ご本人が生理痛のせいで生活に支障が出ていれば診断となります。そのため実態の把握が難しいですが、あるデータによればほとんどの女の子が生理痛に悩んでいて、20〜40%は日常生活に影響が出ているとされており無視できない問題です 1)。
診察
問診と必要に応じて身体診察が行われますが、当院は院長も私も男性医師なので診察中は必ず女性スタッフが同席いたします。問診は生理のこと以外にも性交渉の有無などプライベートな質問があるのでご家族が一緒に来院されている場合でもご本人の希望がない限りは原則お一人で話を伺います。また、答えたくない質問に無理に答える必要はありませんし、仮に喫煙や飲酒などについて「ある」と答えても親や学校に連絡がいくことはありません。
身体診察では精度が高いのは腟からの診察になりますが、性交渉未経験であったりそもそも気が進まなかったりということがあればお腹の触診や超音波検査に切り替えます。いずれにしてもご本人の意思を尊重しながらの診察になるので安心していただいて大丈夫です。
治療
治療法は様々ですが、よく使われるのは痛み止め、漢方、低用量ピルです。痛み止めは最もシンプルな治療で、市販薬でも有効な場合は病院に通う手間も省けます。もし生理痛が思ったように良くならない場合、生理の時期がある程度よめるのであれば生理開始直前から1日3回など予め服用し始めると痛みがコントロールしやすくなることもあります。
漢方は体質改善的な働きが期待できます。安価であり比較的導入しやすいですが、苦くて粉なうえに1日3回の服用を継続する必要があるのが難点です。加えて効果の発現までに要する時間が人によって異なることと、必ずしも全員に一定の効果が期待できるわけではありません。
低用量ピルは避妊薬という印象が強いかもですが、生理も軽くしてくれます。痛みだけでなく出血量も減るのでそちらでもお悩みの場合はより強く効果を実感できるでしょう。加えて月経前症候群の改善、ニキビの抑制や望まない妊娠を防ぐ効果もあります。製剤によっては生理回数を減らしたり、生理のタイミングを自分でコントロールすることもできるため思春期の女性にとってはとても良い選択肢です。「避妊ピル」というとなんだか使うのが恥ずかしくなってしまう人もいるかもですが、当院でも生理痛の緩和を目的に処方を受けている中高生の女の子はたくさんいらっしゃるので身構えすぎる必要はありません。
上記以外の治療としては、子宮内避妊リング(ミレーナ®︎)も選択肢となりますが、思春期では初交(初めてのセックス)がまだだったり子宮内への器具の挿入に抵抗感が強いことも多く実際に使用されることは少ないです。ただ、効果は高いですし、10代に使用できないということは全くありませんので興味があれば是非ご相談ください。
まとめ
というわけで本日は思春期女性の生理痛についてお話ししました。生理痛は人によって重さが違うこと、男性には分からないことなどが理由で周囲に理解されにくい悩みの一つです。特に10代の女性では周囲に相談しにくかったり産婦人科受診へのハードルが高かったりと解決が難しい問題かもしれません。しかし素敵な思い出や経験を重ねる思春期の貴重な時間が生理痛で台無しされるのは勿体無いです。当院ではできるだけご本人の気持ちに寄り添った形で丁寧に診察を進めるよう心がけておりますので是非安心して受診していただければと思います。
1) Aalia Sachedina, et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Feb 6;12(Suppl 1):7-17