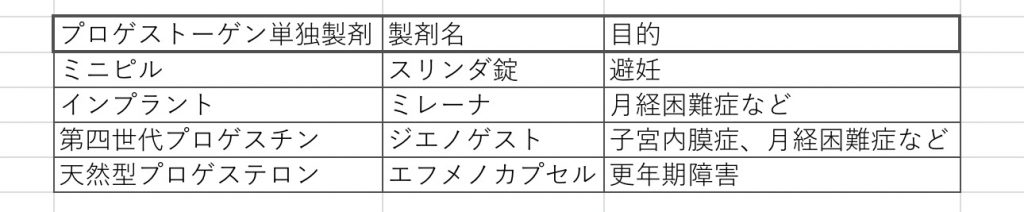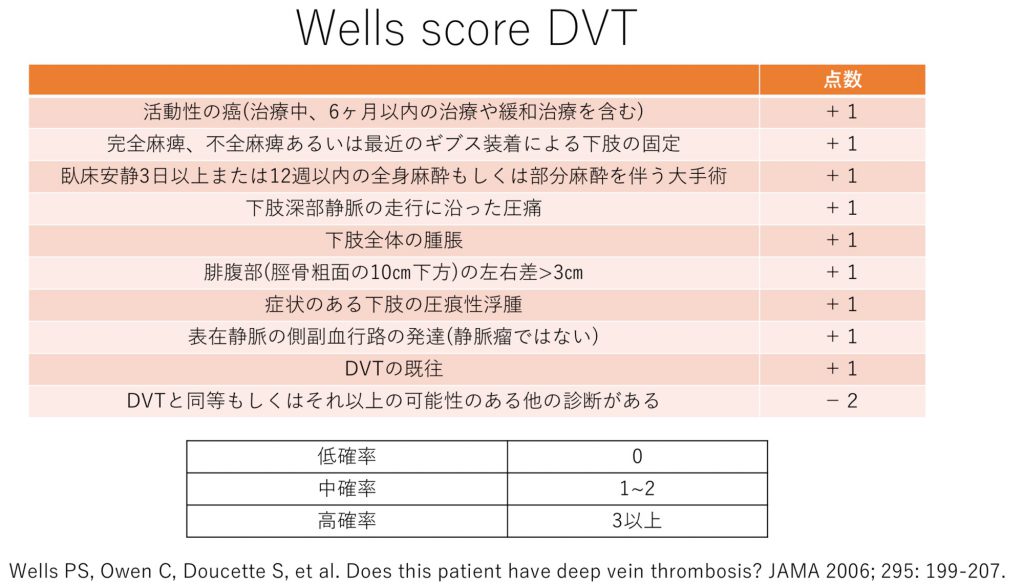こんにちは、副院長の石田です。
40代に入るとホットフラッシュや発汗、イライラ、ウツウツなど更年期症状が出てくる女性が多くいらっしゃいます。これらは年齢を重ねたことによる卵巣機能の低下のために女性ホルモンが少なくなった結果として起こります。治療としては不足した女性ホルモンを薬で補うホルモン補充療法(HRT)が一般的ですが、始めたはいいもののいつまで続けたらいいのか不安になっている女性も少なくありません。そこで本日はHRTの継続期間についてお話ししたいと思います。
ホルモン補充療法の継続期間
一般的には投薬5年目、もしくは60歳が近くなってきたら「そろそろやめますか?」と医師から声がかかりやすいのかなという印象があります。これは投薬5年目以降で乳がんの発生率が上昇する可能性を、そして60歳を過ぎると新規のHRT開始に関しては心臓発作や血栓の発症率が増加する可能性をそれぞれ示唆する研究があること、加えて何となく数字的にもキリが良いことからそうなっているのかもしれません 1)2)3)。ただ、実際にはHRTをどのくらい続けるべきかについては決まった見解はありません。女性ホルモンの欠乏症状は早ければ治療開始から数年程度で治ってくることが多い一方で、人によっては強い症状が10年以上続くこともあります。そのため日本国内だけでなく国際的にもHRTの継続期間については一人ひとりの女性のコンディションに合わせて調整していきましょうということになっています 4)5)。具体的には1年に1回は続けるべきかどうかを治療効果や年齢、検査などを踏まえて検討する約束になっています。
まとめ
本日はホルモン補充療法はどのくらい続けるのかについて解説しました。上記の通り、お薬を使用する期間については人によって差がありますが、一般的な話をすると目立った副作用が無く効果が得られている場合は2〜5年程度使う人が多いような気がしていますし、実際イギリスの政府機関のウェブサイトにもそんな感じで書いてありました 6)。いずれにしてもゼロリスクの治療はありませんので、治療によって得られるメリットと続けるリスクを天秤にかけながら判断し続ける必要がありますので、現在治療中の患者さんにおかれましては主治医としっかりコミュニケーションをとっていただくのが良いと思われます。
参考文献
1) Rowan T Chlebowski, et al. JAMA. 2003 Jun 25;289(24):3243-53.
2) Jacques E Rossouw, et al. JAMA. 2007;297:1465-1477.
3) Mary Cushman, et al. JAMA. 2004:292:1573-1580.
4) 日本産科婦人科学会・日本女性医学学会. ホルモン補充療法 ガイドライン. CQ403.
5) T J de Villiers, et al. Climateric. 2016 Aug;19(4):313-5.
6) National Health Service. When to take hormone replacement therapy (HRT).